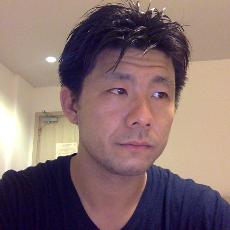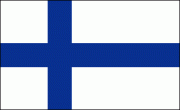TOP/海外インターン体験談(タイモブログ)を読む/インドの体験談:日本の衰退産業、農業に活路を見いだせるか
日本の衰退産業、農業に活路を見いだせるか
- 2016/12/15 00:00
- インド
- 営業,社長直下
- インターン前
農林水産省によると 2014年度の農業総産出額8兆3639億円。 平成7年の10兆4498億円を境に年々成長率は下落の一途をたどり、現在の8兆円の水準に落ち着いたのが2006年だ。現在の水準は昭和59年のピーク時の11兆7171億円に比べると71%も下落している。
また2014年度、日本のGDPに占める農業総産出額の割合はわずか1.6%に過ぎず、1960年に86%だった日本の食料自給率(生産額ベース)は2015年には66%にまで低下している。
農業労働力に関する統計によると戦後1000万人を超えていた農業人口は2016年現在では192万人になり、従事者の66歳を超えている。
こうした状況を受けて、農林水産省は、日本の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高齢化が進行しており、農業構造のぜい弱化が進んでいるとの見解を示してしている。
安倍内閣では、2013年に閣議決定された、日本経済の再生に向けて展開する「3本の矢」である「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「成長戦略」のうち「成長戦略」の一つに「攻めの農林水産業」を掲げ農業の活性化と再興を喫緊の課題としている。
具体的な政策として第1次産業としての農業、第2次産業としての製造加工業、第3次産業としての小売業、サービス業の事業を掛け合わせた農業の6次産業化や農地法改正による規制の緩和を盛り込んでいる。
平成21年の改正では農業法人でない一般法人も農地の借用が認められるなど大幅な規制緩和が行われ、今年2016年には一般企業による農地の所有に対する規制を緩和した。
この流れを受けて2008年には400社あまりだった新規参入企業数が2015年にはその4倍以上である1898社に増えている。
農業は一年の中で作物の収穫時期と期間は限られており、農家の実質的な現金収入は作物が収穫できる期間のみだ。収穫が終ると次の作物を育てるための準備期間に入る。
この時期は現金収入がほとんどないにもかかわらず作物の苗の購入、設備投資、人権費等の様々なランニングコストが重くのしかかる。
そのため多少体力のある企業でも短期的な収益を期待している企業は次々と撤退して行く。自営業や家族経営の場合は兼業がスタンダードになっている。
軌道に乗るまでは少なくとも3年から5年はかかると言われており、長い目で「農業ビジネス」を育て上げた企業だけが恩恵を受けられる世界だ。
そのためITソリューションを基軸とした農業生産のサポート事業を手がける新規参入ベンチャーが近年増加傾向にある。具体的には収穫情報を提供するクラウドサービスや 経営分析、情報管理、農作業ロボット、直売所のPOSシステムなどである。
2013年時点の農業関連のITサポート事業の市場規模が66億円となっている。矢野経済研究所の推計によると2020年までには308億円の市場規模の拡大を見込んでいる。
また収穫情報などの情報管理クラウドサービスに限らずインターネット上で委託販売や直接販売のルートを提供するプラットフォームを手がけるベンチャーも隆起してきており、農協の役割が代替され、農家がJAに頼らず独立独歩で経営を行う体勢が整いつつある。
今後、農業生産において収益構造を支える技術革新が成長戦略を支える一つの鍵になるのではないかと思う。
お気に入り登録数:0
関連海外インターン体験談(タイモブログ)

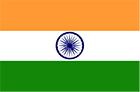
2025.04.19 鈴木雅也さん
【海外インターン参加者インタビュー】未知にワクワクしなが...
職種

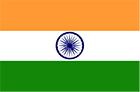
2025.04.18 M.A.さん
【海外インターン体験談】 実際に海外で働くことで得た、かけ...
職種その他

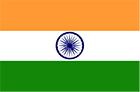
2024.11.26 奥西夏季さん
【海外インターン参加者インタビュー】現場での経験は一番に...
職種その他

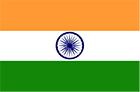
2018.01.18 ユウキ
逸脱行動者と言われた女性がインドで学習塾を立ち上げるまで
職種企画・マーケティング,社長直下,その他

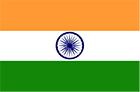
2017.02.19 ひろ@インド
【海外インターン体験談】インドでのインターン半年間の総括!
職種営業,新規事業,社長直下